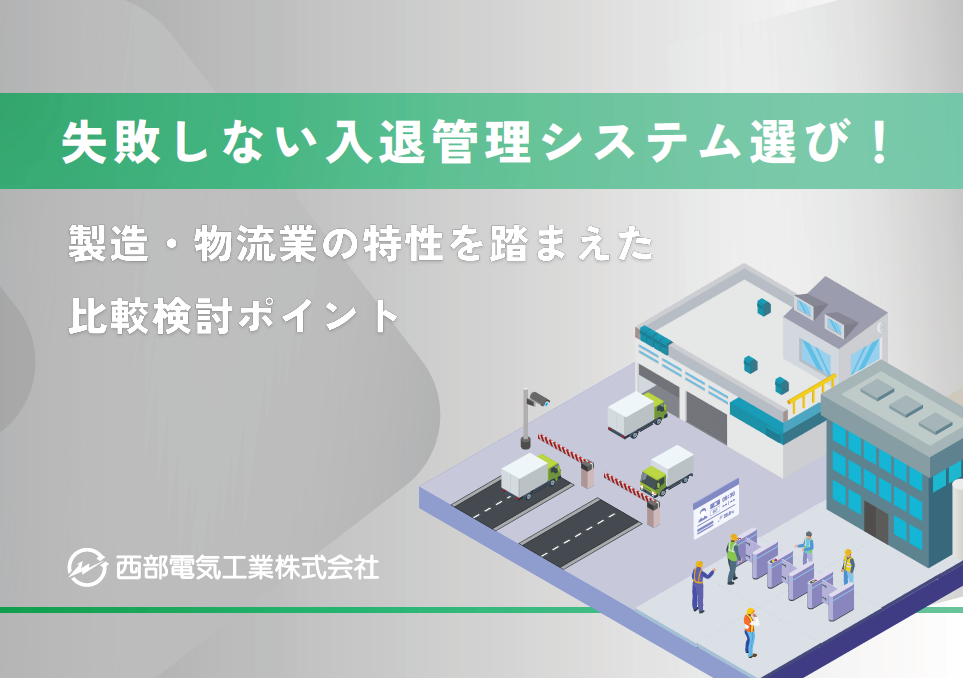2024年問題の解決策とは?物流業界の課題や展望を解説

2024年、物流業界は大きな転換点を迎えました。働き方改革関連法の適用により、トラックドライバーの時間外労働が大きく制限され、従来の長時間労働に依存した輸送体制の維持が困難になりつつあります。
ただ、2025年になっても依然として多くの問題は残されたままであり、多くの企業は早急な解決策の実施が求められています。
この「2024年問題」は、単に運送業界だけの課題ではありません。 荷主企業が主体的に対策を講じなければ、サプライチェーン全体に深刻な影響を及ぼす可能性があります。このような厳しい環境の中で、企業はどのようにして物流業務を最適化し、安定的な輸送網を維持すべきなのでしょうか。
本記事では、物流業界が抱える課題を整理し、デジタル技術の活用や、入退管理ソリューションなどの解決策を交えながら、今後の展望について詳しく解説します。
製造・物流業向け入退管理システム比較検討ポイントをダウンロード【資料はこちら】
- 目次 -
物流業界の2024年問題とは?

2024年、物流業界は大きな転換点を迎えています。特に「2024年問題」と呼ばれる課題は、運送業界の現場だけでなく、荷主企業を含むサプライチェーン全体、そして私たち消費者の生活にも影響を及ぼすものです。
この問題の根本には、「働き方改革関連法」 による労働時間の規制があります。特に、トラックドライバーの時間外労働の上限が年間960時間に制限されることで、長時間労働が常態化していた物流業界に大きな制約が生まれました。この結果、物流業務全体の輸送能力が低下し、業界や社会にもたらす問題が深刻化すると予測されています。
また、2024年問題は一過性のものではありません。労働時間の規制が進むことで、ドライバー不足の問題はさらに加速し、企業は新たな配送体制の構築を迫られています。さらなる負担の増加、そして消費者の負担増大にも影響を及ぼすでしょう。
参考サイト:物流の「2024年問題」とは – 国土交通省 東北運輸局
物流の2024年問題の原因

物流業界が直面している2024年問題の中心には、働き方改革関連法による労働時間の規制があります。
労働時間規制による大幅な稼働率の低下
これまで、長時間労働が常態化していた運送業界では、労働環境の改善が求められていました。その一環として、トラックドライバーの時間外労働が制限されることになり、これが輸送能力の低下を招くと懸念されています。
これまで多くの運送企業は、長時間労働に頼ることで配送スケジュールを維持してきました。しかし、新たな規制によって残業時間の上限が引き下げられるため、これまでと同じ運送業務をこなすことが難しくなります。
特に長距離輸送を担うドライバーにとっては、これまで1日で運べていた距離を走れなくなる可能性があり、輸送の遅延やコスト増加といった影響が避けられません。
現場の人材不足
さらに、物流業界は以前からドライバー不足が深刻化しており、2024年問題はその影響をさらに加速させる要因となるかもしれません。現在、トラックドライバーの平均年齢は50歳を超えており、今後、引退する人が増える一方で、新たな人材の確保は難しくなっているのが現状です。
特に若年層は、長時間労働や厳しい労働環境を理由に運送業界を敬遠する傾向が強く、根本的な人手不足の解消には至っていません。
このように、2024年問題は単なる労働規制の強化ではなく、物流業界の構造そのものを変える必要がある大きな転換点をもたらしました。企業は、労働環境の改善と並行して、業務効率の向上や新たな輸送方法の確立に取り組むことが重要です。
物流の2024年問題がもたらす悪影響

2024年問題による労働時間規制は、物流業界にとって今後の運営に深刻な影響を及ぼします。
特に、ドライバーの勤務時間を大きく制限し、従来の業務スケジュールの維持が困難となるため、輸送能力の大幅な低下を引き起こします。すでに人手不足が深刻化している中で、規制がさらにドライバー不足を加速させ、業界全体にさらなる負担を強いることは避けられません。
また、これまで長時間労働でカバーしていた配達スケジュールが乱れ、納期遅延が起こるリスクが高まります。
上記のような状況を踏まえ、以下では2024年問題がもたらす具体的な影響を3つ解説します。
配送遅延の発生
ドライバーは労働時間の上限があるため、一日に走行できる距離や配送回数が制限されるようになっています。特に長距離輸送を担うドライバーにとっては、今まで1日で運べていた距離を走れなくなるケースが増えつつあるのが現状です。このことから、サプライチェーンにおいては、工場等からの製品の出荷や、必要な資材の納入に遅延が発生する可能性が高まります。
従来のスケジュール通りの配送が困難になり、納期遅延が多発する可能性が高まります。
トラック不足による出荷滞留
ドライバーの労働時間が制限されると、当然ながらトラックの稼働時間も短縮されるため、物流拠点ごとの輸送能力が低下します。その結果、積み込むべき荷物が倉庫や配送拠点に滞留し、出荷遅延が発生する事態を招くでしょう。
これが続くと、物流拠点の在庫スペースが圧迫され、業務オペレーション全体が停滞することになります。
物流拠点周辺の交通渋滞の悪化
配送を担当する人材不足の他にも、物流拠点周辺での交通渋滞悪化も懸念されています。
トラックの荷積み・荷下ろしの待機時間が増加すると、物流拠点周辺の渋滞が発生に繋がるからです。特に都市部や主要幹線道路沿いに位置する倉庫・工場では、長時間待機するトラックが車線をふさぎ、一般車両の通行を妨げることが懸念されます。
この渋滞が慢性化すると、物流業務の遅延のみならず、周辺住民や企業の通勤・業務にも支障をきたし、地域経済全体に影響を及ぼしかねません。さらに、緊急車両の通行が妨げられるリスクもあり、渋滞対策の強化が急務となっています。
これらの問題を放置しておけば、物流業界は致命的な打撃を受け、経済活動全体に波及する恐れもあります。そのため、企業は一刻も早く労働環境の改革と業務効率化に取り組む必要があります。
デジタル技術を活用した効率化で課題解決を

物流業界が直面する2024年問題を乗り越えるためには、労働力の減少に対応しつつ、業務の効率を最大化することが不可欠です。そのためには、デジタル技術の活用が鍵となります。
現在、物流業界ではAIやIoTを駆使したシステム導入が進められており、業務の最適化が図られるようになってきました。入退管理のデジタル化や自動運転技術、ドローン配送といった革新的な技術が、物流業務の変革をもたらす可能性を秘めています。その中でも、入退管理プロセスのデジタル化は、直接的な効率化効果が見込める分野です。
西部電気工業の「入退管理ソリューション」
物流の効率化において、倉庫や物流拠点でのオペレーション改善は避けて通れません。その中でも、物流センターにおける「入退管理」は、多くの企業にとって課題となっています。従来の常駐警備員による紙ベース管理などのアナログな手法では、入退管理の遅延による車両の滞留が発生し、ドライバーの待機時間が長引くだけでなく、近隣住民への騒音や渋滞といった影響も無視できません。結果として、無駄な労働時間が発生し、物流のスムーズな流れが阻害されることが問題視されています。
こうした課題に対応するため、西部電気工業は2024年問題における「荷待ち」や「待機時間」の削減を重要な課題と捉え「FLOWVIS(フロービス)」と「すいすい入退+(すいすいにゅうたいプラス)」という入退管理ソリューションを提供しています。
「FLOWVIS」は、物流拠点の車両入退管理を「ETC」認証と「車番」認証の両方を用いて可視化することで、スムーズな出入りを実現し、施設の稼働効率を向上させます。一方、「すいすい入退+」は、「RFID」認証を用いてタッチレスでの人・車・二輪車の入退管理を可能にし、物流のスピードを損なうことなく、セキュリティの向上にも貢献します。
2024年問題によるドライバーの労働時間制限を考慮すると、物流拠点での待機時間を削減することは極めて重要です。入退管理が適切に行われることで、無駄な滞留を防ぎ、近隣住民への影響を軽減するだけでなく、限られた労働時間を最大限に活用することができます。
これにより、ドライバーの負担軽減と業務の効率化が同時に実現され、物流の生産性向上につながります。
製造・物流業向け入退管理システム比較検討ポイントをダウンロード【資料はこちら】
まとめ
2024年問題による労働時間の規制は物流業界に大きな影響を及ぼし、ドライバー不足や倉庫作業の負担増加、物流拠点周辺の渋滞といった問題を引き起こします。
加えて、労働人口の減少が予測されており、今後、物流の維持そのものが困難になる可能性があります。こうした課題に対応するため、デジタル技術の活用が不可欠です。
西部電気工業では 「FLOWVIS」 や 「すいすい入退+」 などの入退管理ソリューションを提供し、荷待ち時間の削減や物流拠点の効率化を支援しています。今後も業界の皆様とともに、物流の効率化と生産性向上を進めることで、持続可能な物流体制の構築を目指して参ります。
更新日:2025.04.25