新物流効率化法(新物効法)で物流現場はどう変わる?2025年施行の法改正のポイントを解説

2024年4月にトラックドライバーの時間外労働規制が強化されて以降、物流業界は「物流の2024年問題」と呼ばれる深刻な課題に直面しています。これを受けて政府は物流関連法を大幅に改正し、2025年4月1日より「新物効法(新物流効率化法)」が施行されました。
近年、物流業界では労働時間規制が注目され続けており、今後も法改正によって、現在は努力義務にとどまっている内容が、さらに強化される可能性があります。そのため、「自社はまだ大丈夫」と油断せず、早めに対応することが重要です。
本記事では、新物効法への法改正により物流現場にどのような変化が生じるのか、旧法との違いや改正点、2025年秋に予定されている「判断基準に基づく調査・公表」の内容、入退管理に向けた実践的な対策について解説します。
製造・物流業向け入退管理システム比較検討ポイントをダウンロード【資料請求はこちら】 ▶
- 目次 -
2025年施行の新物効法とは?旧法との違い
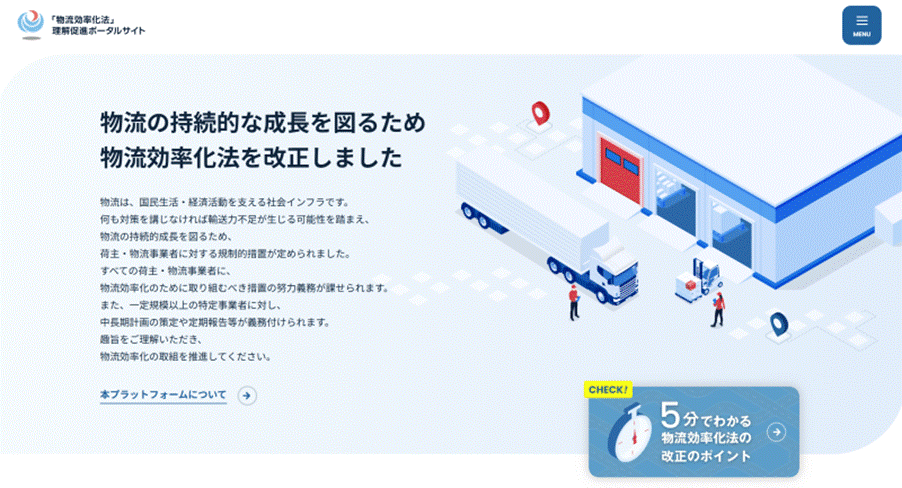
新物効法とは、正式名称を「物資の流通の効率化に関する法律(物流効率化法)」といい、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(物流総合効率化法)」および「貨物自動車運送事業法」の一部を改正した法律です。
改正日と施行日は、以下の通りです。
・改正日(公布):2024年5月15日
・施行日:2025年4月1日(主要条文)、一部は2026年春までに段階的施行
旧法である「物流総合効率化法」との違いは、旧法が支援を中心としていたのに対し、新法では規制を強化する方向へ転換された点にあります。
具体的には、荷主や物流事業者に対して物流効率化への取り組みを努力義務として課し、国がその取り組み状況を調査・公表・指導・命令できる仕組みが導入されました。
新物効法が必要とされる背景には、2024年4月から始まったトラックドライバーの時間外労働規制、いわゆる「物流の2024年問題」による輸送力不足の懸念があります。
新物効法は、物流の効率化や商慣行の見直しと、荷主・物流事業者・消費者が一体となった行動変容を促し、持続可能な物流基盤を整えるための抜本的な法改正といえるでしょう。
新物効法の主な法改正ポイント

新物効法では、従来の支援中心の仕組みから、荷主や物流事業者に具体的な義務・努力義務を課す規制的な仕組みへと大きく転換されました。新物効法に対応するためには、改正ポイントを正しく理解することが重要です。
新物効法への法改正による変更点は、大きく以下の3つです。
- 荷主・物流事業者に対する規制的措置
- トラック事業者の取引に対する規制的措置
- 軽トラック事業者に対する規制的措置
ここでは、それぞれの改正ポイントを解説します。
1.荷主・物流事業者に対する規制的措置
「荷主・物流事業者に対する規制的措置」は、旧法「流通業務総合効率化法(物流総合効率化法)」から変更された法律です。改正ポイントは、下記2点に整理されます。
・すべての事業者に対する努力義務の拡大
・一定規模以上の事業者(特定事業者)への義務付け
それぞれの詳細を見ていきましょう。
1.すべての荷主・物流事業者に対する努力義務(2025年度施行)
新物効法では、発荷主・着荷主、トラック・鉄道・港湾運送・航空運送・倉庫など、すべての事業者に対し、物流効率化に向けた措置を講じる努力義務が課せられました。
具体的には、ドライバーの荷待ち時間の短縮や積載効率の向上などが挙げられます。さらに、元請トラック事業者や利用運送事業者には荷主への協力義務が追加され、フランチャイズチェーンの本部にも荷主に準ずる義務を負うことになりました。
これらの取り組みについては、国が調査・公表を行い、必要に応じて助言や指導を実施します。
2.一定規模以上の事業者(特定事業者)に対する義務(2026年度施行)
一定規模以上の荷主や物流事業者は「特定事業者」として指定され、中長期計画の作成や定期報告が義務付けられます。
また、特定事業者である荷主は「物流統括管理者」を選任することも義務化され、組織的に物流改善に取り組む体制を整えることが求められます。
なお、特定事業者の取り組みが著しく不十分な場合、国は勧告・命令を行うことができます。命令に従わなかった場合には、命令違反罪として100万円以下の罰金 が科される規定も盛り込まれました。
これにより、従来の努力目標にとどまらず、実効性を伴った取り組みが強制される仕組みとなっています。
出典:5分でわかる物流効率化法の改正のポイント|物流効率化法 理解促進ポータルサイト|国土交通省、経済産業省、農林水産省、新物効法について|国土交通省
2.トラック事業者の取引に対する規制的措置
新物効法では、トラック事業者の取引に関して契約や管理体制の透明性を高め、下請取引の適正化を図るための規制が強化されました。
具体的な法改正のポイントは、以下の3点です。
・書面による交付義務
・実運送体制管理簿の作成義務
・下請事業者への発注適正化について努力義務と、一定規模以上の事業者(特定事業者)には管理規程の作成、責任者の選任を義務付け
1.書面による交付義務
運送契約を結ぶ際に、提供する役務の内容や対価(附帯業務料・燃料サーチャージなど)を明記した書面の交付が義務付けられました。これにより、契約条件の明確化とトラブル防止が期待されます。
2.実運送体制管理簿の作成義務
元請事業者は、実際に運送を担う事業者の名称などを記載した「実運送体制管理簿」を作成することが義務化されました。これにより、運送体制の透明性が確保されます。
3.下請事業者への発注適正化について努力義務と、一定規模以上の事業者(特定事業者)には管理規程の作成、責任者の選任を義務付け
下請事業者への発注適正化は、すべての事業者に努力義務として課されています。さらに、一定規模以上の事業者(特定事業者)は、発注管理に関する規程を整備し、専任の責任者を置くことが義務となりました。
3.軽トラック事業者に対する規制的措置
新物効法では、軽トラック事業者についても安全性と法令遵守を強化するための規制が導入されました。法改正のポイントは、以下の通りです。
・管理者の選任と講習受講の義務化
・事故報告の義務化
・情報公開の拡充
1.管理者の選任と講習受講の義務化
軽トラック事業者は、必要な法令知識を担保するため、管理者を選任し講習を受講させることが義務付けられました。
2.事故報告の義務化
軽トラック事業者は、事故発生時に国土交通大臣への報告を行うことが義務化されました。
3.情報公開の拡充
国交省ホームページでの公表対象として、軽トラック事業者の事故報告や安全確保命令に関する内容が新たに追加されました。
2025年秋に予定される「判断基準に関する調査・公表」

2025年秋と2026年秋には、新物効法に基づき「判断基準に関する調査・公表」が実施される予定です。これは、荷主や物流事業者が物流効率化にどの程度取り組んでいるかを国が調査し、その結果を点数化して評価・公表する仕組みです。
優れた取り組みを行っている企業は「好事例」として紹介される一方、改善が必要な企業についても明示されるため、業界全体の意識改革を促す効果が期待されています。
なお、この調査結果はトラック・物流Gメンや公正取引委員会とも共有され、場合によっては指導・助言、さらには命令といった行政措置に発展する可能性もあります。
物流効率化は今や一部の企業だけの課題ではなく、業界全体の競争力や持続可能性に直結する重要なテーマですが、いまだ十分な対応を取っていない企業も見受けられます。
近年、物流関連の法改正は相次いでおり、努力義務が今後さらに強化される可能性も否定できません。「自社は大丈夫」と油断するのではなく、早い段階から体制の見直しや改善に着手しておくことが、今後の生き残りに不可欠といえるでしょう。
2025年新物効法の施行に伴う課題と対策

新物効法の施行により、荷主や物流事業者は具体的な現場課題に直面しています。特に大きなテーマは「荷待ち・荷役時間の削減」であり、これを実現できなければドライバーの労働時間規制にも対応できません。
また、物流統括管理者を中心とした社内体制の整備や、突発的な外部業者の来訪・短期契約者への管理体制も求められます。
さらに、2025年秋以降の調査・公表では企業の取組みが可視化されるため、企業イメージや取引への影響も懸念されます。早期から自社の弱点を洗い出し、法改正に対応するための改善ロードマップを描くことが重要です。
新物効法への対応に役立つツール例
新物効法への対応を円滑に進めるためには、「業務の見える化」と「仕組み化」が欠かせません。
例えば、荷待ちや滞留時間を計測できる「可視化ツール」を導入することで、ボトルネックの把握と改善が容易になるでしょう。また、「入退管理システム」は、突発的な外部業者や短期的な委託業者への対応に役立ちます。
さらに、物流統括管理者が中心となり、中長期計画をフォーマット化して運用することで、調査・公表時の評価リスクを低減することが可能です。
実効性ある取り組みを継続することで、法令対応だけでなく、取引先や消費者からの信頼確保にもつながります。
新物効法への法改正に際し、西部電気工業の入退管理ソリューションが果たす役割
2025年4月に施行された新物効法により、荷主や物流事業者には物流効率化への具体的な取り組みが求められるようになりました。現場では、「荷待ち時間の短縮」「外部業者の管理強化」「滞留時間の可視化」といった課題が特に注目されています。
西部電気工業は、こうしたニーズに応えるため、入退管理や動線の見える化を支援するソリューションを提供しています。ここでは、新物効法への法改正に対応するために有効な、3つの入退管理ソリューションの概要をご紹介します。
すいすい入退+(すいすいにゅうたいプラス)
引用:RFID入退管理システム『すいすい入退+』| 西部電気工業ソリューション
「すいすい入退+」は、RFIDを活用して人や車両の入退場を自動で管理できるシステムです。RFID(Radio Frequency Identification)とは、電波を使ってICタグの情報の読み取りや書き込みを行う技術です。
UHF帯(超短波帯)のRFIDタグを使用するため、タッチ操作は不要で、離れた場所からでも人・車・二輪車を検知します。これによりゲート前での停止や手続きが省け、渋滞緩和や利用者・管理者双方の負担軽減に効果的です。
さらに、入退記録は自動的に蓄積されるため、トレーサビリティ(追跡可能性)や安全管理の強化にもつながります。結果として、荷待ち時間削減や動線の最適化に寄与し、新物効法が掲げる効率化に直結する仕組みです。
APOTORO(アポトロ)
引用:【QRコード来訪者予約受付システム】APOTORO | 西部電気工業ソリューション
「APOTORO」は、突発的な来訪者や期間限定業者に対応する予約型入退場管理システムであり、新物効法が示す「外部業者を含めた効率化・適正管理」に役立つソリューションです。
QRコードや顔認証を使って事前に登録しておくことで、当日の混乱や不透明な入場を防ぎます。これにより、外部業者の管理が強化され、セキュリティと契約の透明性も向上します。
関連記事 :【導入事例】QRコード来訪者予約受付システム『APOTORO』 | 西部電気工業ソリューション
FLOWVIS(フロービス)
引用:【車両入退管理システム】FLOWVIS/フロービス | 西部電気工業ソリューション
「FLOWVIS」は、ETC車載器や車番認識を活用して、車両の入退場を自動で管理するシステムです。登録車両と未登録車両を判別し、バーゲートを制御することで、スムーズな通行と守衛業務の効率化を実現します。
また、入退場履歴や滞在時間を記録することで、荷待ち時間の短縮や安全性向上に役立つほか、待機時間や混雑状況の課題を明確にするのにも有効です。これらのデータは、物流統括管理者が判断を下す際の参考材料としても活用できます。
ここまでご紹介した3つのソリューションは、法令対応だけでなく、日常業務の効率化や安全性向上にもつながる仕組みです。さらに、判断基準に基づく調査・公表にも対応可能な実績とデータも備えています。
西部電気工業の入退管理ソリューションについて詳しい内容は、こちらから資料をご確認ください。
様々な入退管理システムの資料をまとめて請求する【資料一括請求はこちら】 ▶
まとめ:新物効法への法改正を現場改善のチャンスに
物流業界が直面する「物流の2024年問題」を受け、政府は物流関連法を見直し、2025年4月1日から新物効法を施行しました。
法改正の主なポイントは、すべての荷主・物流事業者に対する物流効率化の努力義務の拡大と、一定規模以上の事業者(特定事業者)への義務付けです。
特に現場では「荷待ち時間の短縮」「外部業者の管理強化」「滞留時間の可視化」といった課題が注目されており、今後も努力義務が厳格化される可能性があります。そのため、「まだ大丈夫」と思わず、早めの対応が重要です。
なお、新物効法は単なる規制強化ではなく、持続可能な物流体制への転換の契機でもあります。
西部電気工業は、技術力と現場ノウハウを活かし、荷主企業や物流事業者の現場における課題解決をサポートいたします。法令対応だけでなく、物流効率化や安全性向上といった業務革新にも役立てることが可能です。
物流効率化や現場改善に関心のある方は、ぜひ当社のソリューションをご活用ください。
更新日:2025.09.30





